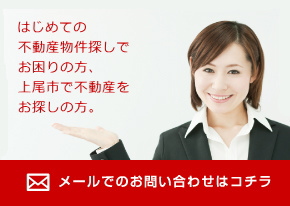空き家については、その処理等を目的とした法律が準備されています。そして、この先で触れていきますが、この法律で想定される一定の空き家に該当すると、様々な規制にさらされることになります。
■「空き家」を対象とした法律がある!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
皆さんが想像する「空き家」とはどのようなものでしょうか。長期間にわたって誰も使用せず、内外装とも(つまり見た目が)だいぶ痛んだ家だろうな…とイメージする人が多いと思いますが、「空き家」には、法律上ちゃんとした定義があります。空き家に関する事項について定めている法律である「空家等対策の推進に関する特別措置法(空き家特措法)」の2条において、「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって、居住その他の使用がなされていないことが常識であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く、と規定されています。
法律なので少し難しい言い回しが含まれていますし、こう書かれてしまうと気持ちが萎えてしまいますよね。もっと簡単に言い換えましょう。「空家等」とは「年間を通じて、誰も住んだり、使ったりしていない建物とその敷地」ということです。ここでいう建物は、住宅に限られませんし、必ずしもボロボロの廃屋だけを指すわけではないのです。※「敷地」も含んだ定義なので、空家「等」となっています。
また、総務省が実施している「住宅・土地統計調査」では、空き家を次の4種類に分類しています。
▼総務省統計局「住宅・土地統計調査」における空き家の分類
①賃貸用の住宅
新築・中古にかかわらず、賃貸のために空き家になっている住宅のこと。総務省の「令和5年住宅・土地統計調査速報集計」によると、全国に443万戸あり、空き家全体(900万戸)の49.2%を占めます。
②売却用の住宅
新築・中古にかかわらず、売却のために空き家になっている住宅のこと。同集計によると、空き家全体の3.7%がこの売却用の住宅です。
③二次的住宅
避暑や保養などを目的として使われる別荘、残業などで遅くなった場合に宿泊する家などの普段は人が住んでいない住宅のこと。同集計によると、空き家全体の4.2%が二次的住宅です。
④その他の住宅
上記①~③以外の人が住んでいない住宅で、転勤や入院などの理由で長期にわたって不在の住宅や、建て替えなどのために取り壊し予定となっている住宅のことです。全国に385万戸あり、空き家全体の42.8%を占めています。
勘の良い人はわかると思いますが、④の「その他の住宅」が、平成10年から令和5年の25年間で約2倍の増加しており、今後も急速に増加していくと予想されています。そして、これが「空き家問題」の中核となる住宅です。本ブログでもこの空き家の問題点と解決方法を中心に解説しましょう。ちなみに、私の実家は大阪府にあり、80歳代後半になる父が所有しています。近い将来、私の実家も④の空き家となるでしょうし、私は老後に実家で暮らすライフプランがありません。空き家となった実家の維持管理を行うモチベーションは高くありませんし、コストをかけるのも抵抗があります。しかし、空き家を放置しておくわけにもいかないのが現実です。

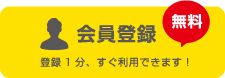
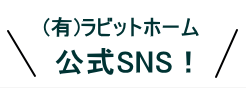
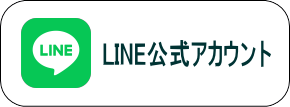









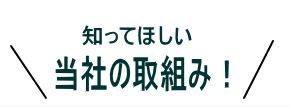


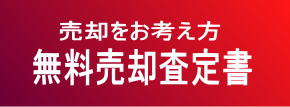
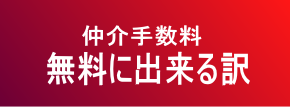
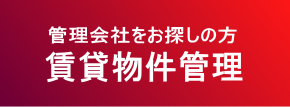

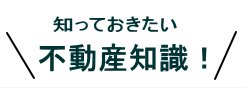
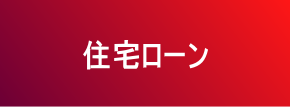





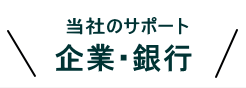




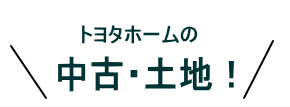
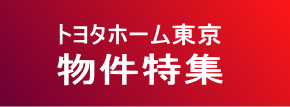
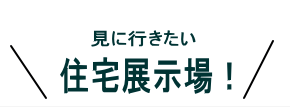
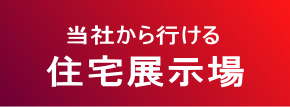
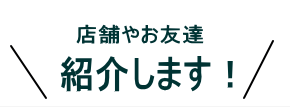


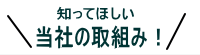


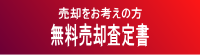

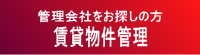

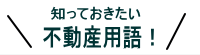
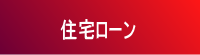





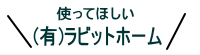


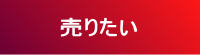

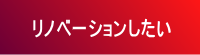

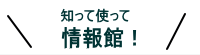

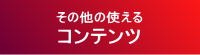
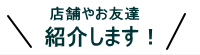

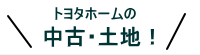
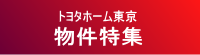
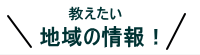



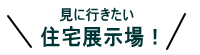
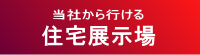
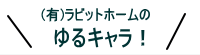

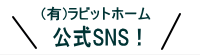






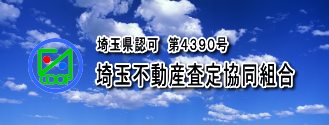

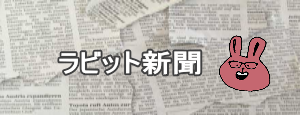




 ・売買会員ログイン
・売買会員ログイン