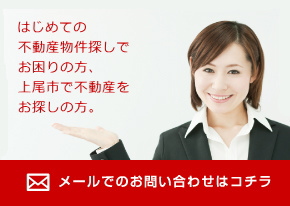相続が発生した場合では、空き家等を複数人(兄弟姉妹等)で共有所有するケースがあります。近年では、このような空き家等の管理を行いやすくするための法改正もなされています。
■共有する空き家の修繕が行いやすく!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
共有とは、1つの物を複数人で所有している状態のことです。要するに、何人かで1つの物を持っている状態のことですね。例えば、親が亡くなり、その親が住んでいた家や土地を兄弟姉妹の3人で相続した場合、その家などを兄弟姉妹の3人の共有名義にするケースがあります。そして、共有には、それぞれの共有者の権利割合を示す「持分」という概念があります。どのくらいの割合で目的物を有しているかという概念です。この点、以前の民法では、数人で共有している空き家を整備するには、どのくらいの整備を行うかにもよりますが、共有者全員の同意が必要とされることがあり、1人でも「費用をかけたくない」と反対したり、連絡がつかない場合、空き家の整備ができずに、空き家が荒れてしまうことがありました。この点、民法が改正され、令和5年4月1日からは、空き家の形状又は効用の著しい変更を伴わない程度の改良を加える行為であれば、共有者の持分の過半数で決定できるようになっています(民法252条1項前段)。
■居所がわからない共有者を除外することも…
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
共有者の中に所在不明の者や、共有物である空き家の管理に無頓着な者がいる場合、一部の共有者が積極的な管理を望んだとしても、持分の過半数の賛成に至らず、空き家等の管理が硬直してしまう事例が見られました。そこで、このような事例に対応するためにも民法が改正され、令和5年4月1日からは、以下の者を除いた共有者の持分の過半数によって、共有物の管理ができることを、裁判所によって決定できる旨の規定が設けられています(民法252条2項)。この改正によって、住民票や戸籍などの調査を経てもなお、存在や所在が不明である共有者などを、共有物の管理に必要な「持分の過半数」から除外できるようになり、空き家の管理が行いやすくなっています。
▼除外できる共有者
①存在を知ることができない共有者
②(存在することは知っているが)所在が不明な共有者
③共有物の管理に関する賛否を求めても、一定期間内に賛否を明らかにしない共有者
■持分は少しでも全部の使用はできる
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
共有については勘違いされやすいですが、持分が3分の1であったとしても目的物全部の使用ができます。例えば、建物を3人で共有する場合、各共有者は1人がリビングのみ、1人がトイレやキッチンのみ…などと限定的な使用ができるものではなく、共有者である以上、自分の持分に応じて、共有物(建物)全体を使用できるのです。

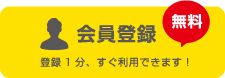
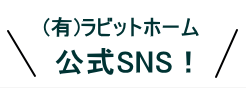
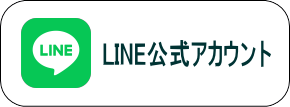









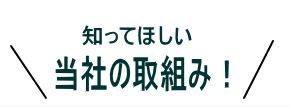


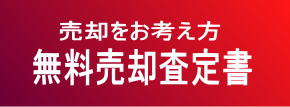
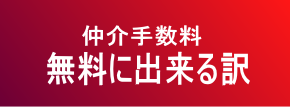
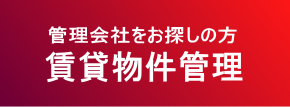

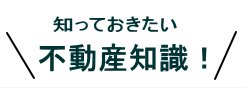
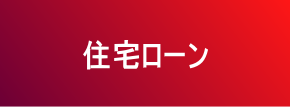





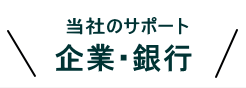




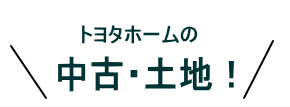
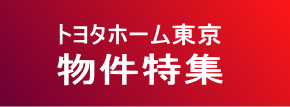
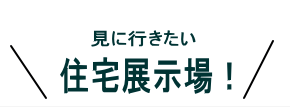
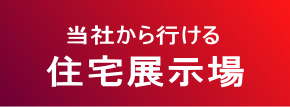
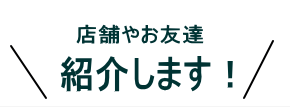


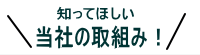


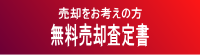

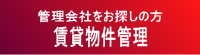

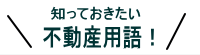
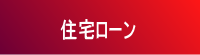





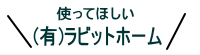


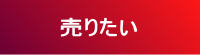

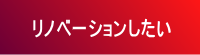

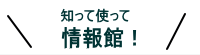

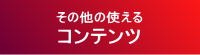
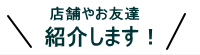

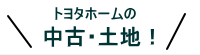
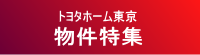
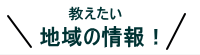



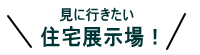
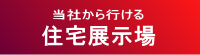
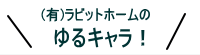

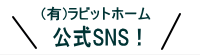






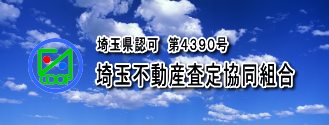

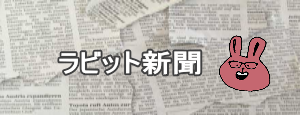




 ・売買会員ログイン
・売買会員ログイン