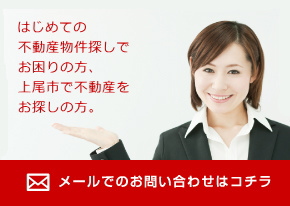以前の法律(民法)では、適法に相続放棄したとしても、相続人となるはずだった者に遺産に含まれる空き家の管理義務が残ってしまうケースがありました。しかし、法改正によりこの義務は緩和され、放棄しやすくなっています。
■住んでいなければ管理が不要に
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
空き家の取得原因の一つに相続があります。そこで、そもそも空き家を相続しないという手段も考えられ、それが相続の放棄という方法です(民法939条)。しかし、以前の民法では、空き家の相続を放棄したとしても、空き家の管理からも解放されるわけではありませんでした。相続を放棄したとしても、次順位の相続人等が空き家の管理を開始するまで、管理し続ける義務があったのです。老朽化した家屋を相続放棄した後、誰も管理しなくなると、近隣住民の迷惑となる可能性がありますよね。それを封じる制度でした。
空き家の相続を放棄しても、管理をしなければならないのであれば、親が多額の借金を抱えていた…という事情でもない限り、相続を放棄するメリットは少ないですよね。そこで、相続放棄の管理義務については、令和5年4月1日からルールが変更され、一定の場合を除いて、相続人に放棄した財産の管理義務がなくなることとなったのです。管理義務がなくならない「一定の場合」とは、相続放棄時点で、相続財産を現に占有している(持っている、住んでいる)場合です。例えば、遠方に住んでいた親の住居については、相続の放棄をしてしまえば、現に占有しているわけではないので管理義務を負いません。この法改正によって、相続放棄をする場合の負担が軽くなっています。
■一部財産だけでは放棄できません
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ただし、相続の放棄については、いくつか注意点があります。相続の放棄は、被相続人(亡くなった人のこと)のすべての財産を放棄しなければならず、特定の財産だけを放棄することができないのです。よって、空き家以外に各種証券や預貯金といったプラス財産がある場合、それらも相続することができなくなります。もし相続財産を選べるのならば、負債(マイナス財産、借金など)だけ相続しないことができてしまいますよね。
もう一つの注意点は、相続の放棄をする場合、その旨を家庭裁判所に申述(申し述べること)しなければならず(民法938条)、その申述は原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければなりません(民法915条1項)。ですので、相続の開始を知った後、自分にとって相続の放棄をすることのメリットのほうが上回るかなど、すぐに調査や検討を始めなければならないでしょう。とはいえ、そのような手段もある…ということを知っておいて損はありません。

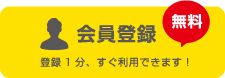
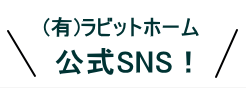
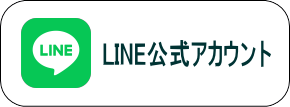









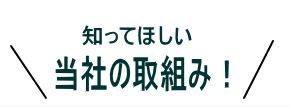


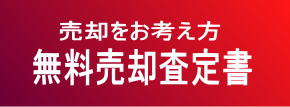
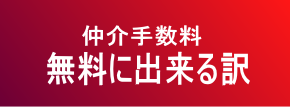
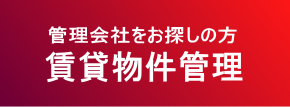

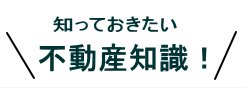
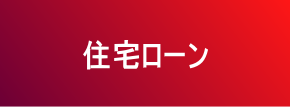





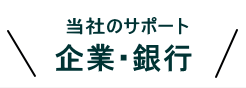




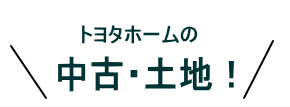
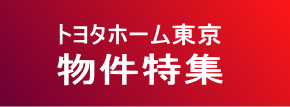
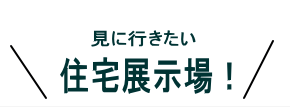
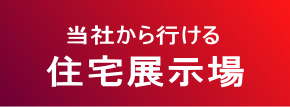
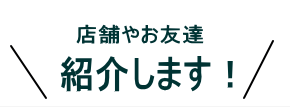


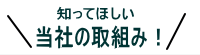


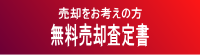

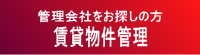

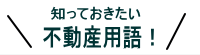
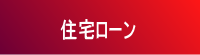





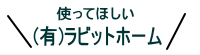


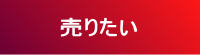

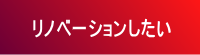

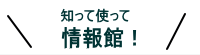

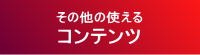
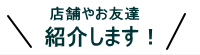

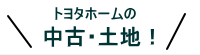
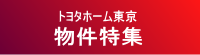
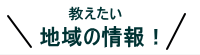



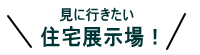
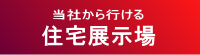
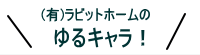

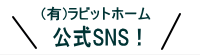






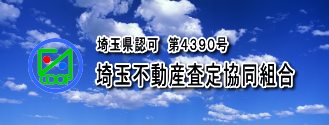

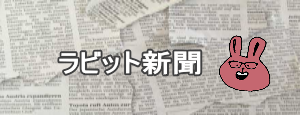




 ・売買会員ログイン
・売買会員ログイン