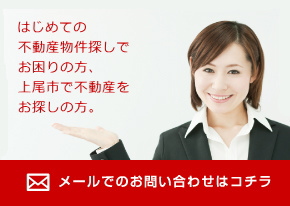誰が相続人となるのかが決まれば、次に各相続人が「どれくらいの割合」で遺産を相続するのかという「相続分」が問題となります。相続分の指定がない場合、民法に規定される「法定相続分」で割合が決まります。
■実際の相続する割合は?
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定相続人(法律で認められる相続人)が決まったとして、次に各相続人が相続する財産の割合が問題となります。それぞれの相続人が相続財産に対して有する権利の割合を相続分といいます。この相続分についても被相続人(亡くなった人)による遺言による指定がない限り、法律で定められています。
▼法定相続分(民法900条)
①配偶者と子が相続人の場合
⇒ともに2分の1ずつ
②配偶者と直系尊属が相続人の場合
⇒配偶者は3分の2、直系尊属が3分の1
③配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
⇒配偶者は4分の3、兄弟姉妹が4分の1
配偶者と子が1人いる場合、相続分は2分の1ずつになります。しかし、配偶者と「子が2人」いる場合であっても、やはり子の全体(全員)の相続分は2分の1なので、その2分の1を2人の子で分け合うこととなり、2人の子の相続分は、それぞれ4分の1ずつとなります。
空き家などの不動産は、分割が難しい場合が通常です。この場合は、【⑥共有する空き家の管理がしやすく!】で触れた共有という方法で共同相続することが多いでしょう。
■話し合いで空き家を相続しない方法も
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
よく耳にする言葉ですが、実はよくわからない制度が「遺産分割」かもしれません。民法は、様々な事情を考慮して、各相続人が取得する遺産を具体的に決めることができると想定しています(民法906条)。要するに、どの相続人が、どの遺産を取得するか…などを話し合って決めることができるというものです。これが遺産分割であり、その話し合いのことを遺産分割協議といいます。遺産の共有状態を解消する制度ともいえます。
遺産分割は、相続が開始された後であれば、原則として、いつでも相続人全員の協議によって行うことができます(同法907条1項)。したがって、「預貯金の相続は少なめでよいから、不動産(空き家)を相続しない」といった旨を他の相続人に主張し、異議が出なければ、その実現が可能かもしれません。つまり、親や兄弟姉妹との話し合いによって、亡くなった親の空き家を自分は相続をせずに他の相続人に承継させるというケースもありえます。
なお、被相続人が生前に遺言を残すことによって、一定期間、自身の死後の遺産分割を禁止することもできますので(同法908条1項)、そのような場合は遺産分割ができません。また、遺産分割が必ずしもまとまるとは限りませんから、そのような場合は、遺産分割の内容について、家庭裁判所の審判等の裁判上の手続きで決定することも可能です(同法907条2項)。

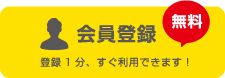
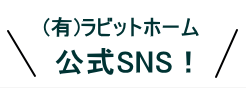
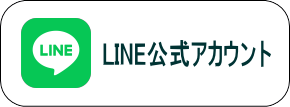









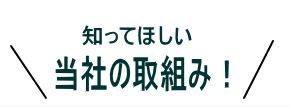


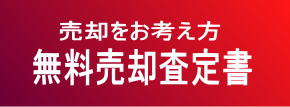
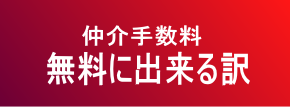
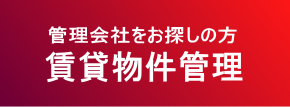

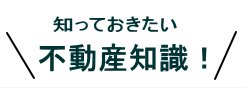
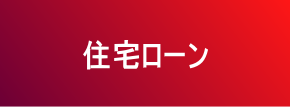





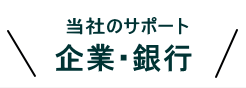




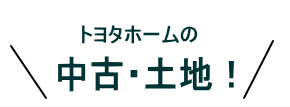
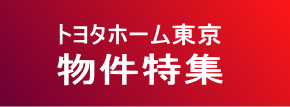
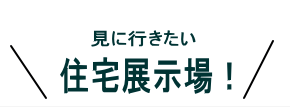
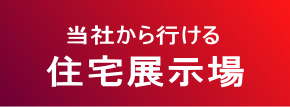
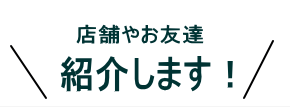


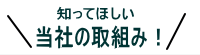


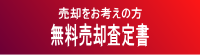

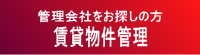

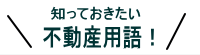
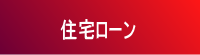





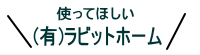


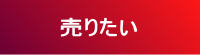

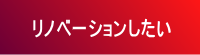

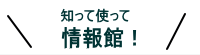

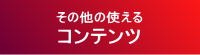
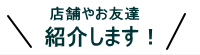

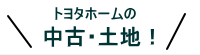
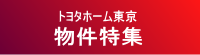
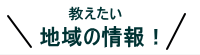



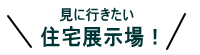
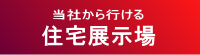
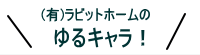

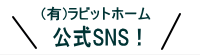






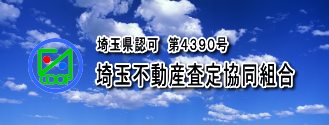

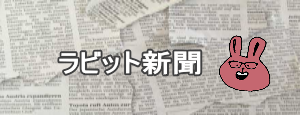




 ・売買会員ログイン
・売買会員ログイン