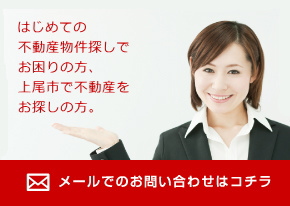令和5年4月27日より「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」という法律に基づいて、使用する予定がなかったり、手に負えない土地を国に引き取ってもらう制度の運用も開始されました。
■「土地」であれば国に委ねることもできる
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
昨日のブログでは、空き家等の持ち主とならないために、そもそも相続をしないという選択肢の話をしました。しかし、あらかじめ両親と話をつめておくなどの準備をしていない場合、難しい判断になるでしょう。この点、一定の費用を負担することで、「土地」については国に引き取ってもらうという制度もあります。これが「相続土地国庫帰属制度」というものであり、令和5年4月27日から運用を開始しています。この制度は運用開始前に生じた相続についても適用があるので、だいぶ前相続したものの「使う予定もないし、引き取ってほしい」という場合にも申請ができます。
さらに、土地の種類は問われないため、宅地のみならず、田畑や山林であっても対象となります。しかし、あくまでも「土地」が対象の制度なので、建物が建っている土地は引き取ってもらえません。よって、土地の上に空き家が残っている場合は、撤去する必要があります。また、国に引き取ってもらうことが決まった場合は、国に10年分の土地管理相当額の負担金を納める必要があります。
土地を手放すことが嫌な場合は、管理業者に管理を委託する場合の費用と比較してみましょう。ただし、管理業者に委託する場合は、10年分以降の管理費も発生します。
■実際には専門家への依頼がお勧め
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
この制度を利用するための条件は少し複雑です。自分で申請する場合は、法務省のホームページで要件をよく確認して、必要な書類が揃ったら法務局で申請前の確認をしてもらいましょう。
国庫帰属にかかる費用は、原則として、土地一筆あたり21万4000円です。はじめに審査手数料として1万4000円を納付し、審査を通過して、国庫への帰属の承認がされた際には、負担金として残りの20万円を支払います。農地や山林の場合は、その広さに応じて負担金の額を計算することになりますので、20万円より大幅に高くなる可能性があります。そして、弁護士・司法書士・行政書士といった法律の専門家には、法律上、この制度の書類作成の代行が認められています。一般の人が簡単に利用できる制度とは言い難いため、専門家に相談するのがお勧めです。
■引き取ることができない土地の例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
・そもそも申請ができないケース(却下事由)
①建物がある土地
②担保権や使用収益権が設定されている土地
③他人の利用が予定されている土地
④土壌汚染されている土地
⑤境界が明らかでない土地、所有権の存否や範囲に争いがある土地
・承認を受けることができないケース(不承認事由)
①一定の勾配・高さの崖があり、管理に過分な費用・労力がかかる土地
②土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
③土地の管理・処分のために、除去すべき有体物が地下にある土地など

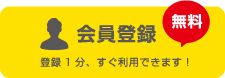
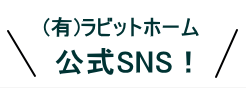
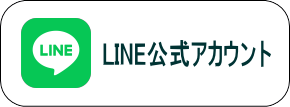









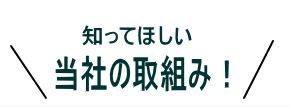


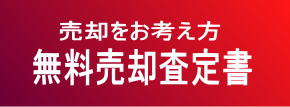
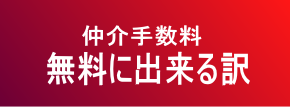
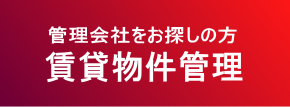

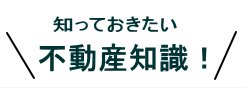
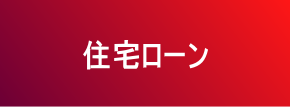





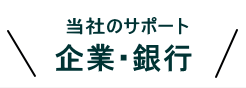




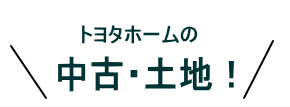
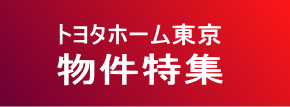
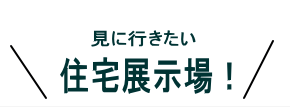
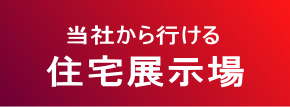
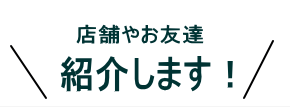


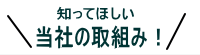


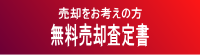

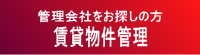

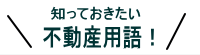
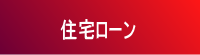





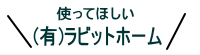


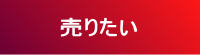

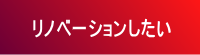

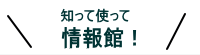

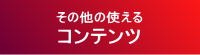
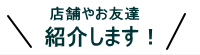

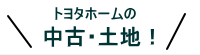
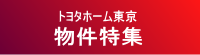
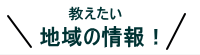



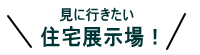
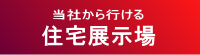
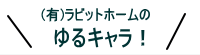

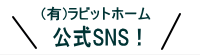






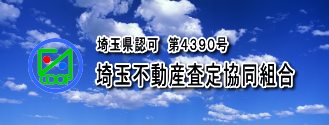

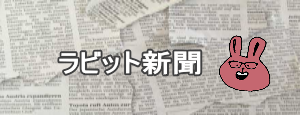




 ・売買会員ログイン
・売買会員ログイン