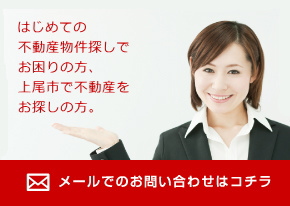ここでは前テーマで触れた遺言のうち、自分でつくれる「自筆証書遺言」の注意点について触れておきます。全文を自分で書く、押印をするといった形式面ではなく、書かれている内容面での注意点があります。
■自筆証書遺言の内容面の注意点
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
遺言書は、被相続人の「最後の意思表示」と言われるものであり、内容について家族が口出しをするものではないことは大前提です。とはいえ、遺された家族の負担を軽くするため、遺言書づくりのアドバイス等の協力をすることは違法ではありません。その他、いくつか遺言の内容面での注意点があります。まずは相続財産の特定方法です。「全財産を妻に相続させる」といったシンプルな内容であれば問題となりませんが、いざ遺言書を書くとなると「あの口座預金は誰々に」「あの土地は誰々に」とつい細かい指定をしたくなるものです。しかし、相続財産の特定方法が不十分な場合、例えば、遺言書に「実家は長男に相続させる」と書いてあったとしても、具体的な不動産の表示がない場合、この遺言書を使って相続登記をすることはできません。正しく記載されていれば、長男が他の相続人の関与なしに単独で登記の申請ができたのに、非常に残念なケースとなります。
この点、少し前に民法が改正され、財産目録については手書きでなくてもよいことになりましたので、もし皆さんが遺言書づくりのお手伝いをすることとなった場合、登記簿謄本や通帳のコピー等を使って、相続財産の正確な特定をしてもらえるよう伝えてみるのも良いでしょう。
次に、遺産の承継方法です。法定相続人が複数名いる場合、相続財産は原則として共有となり、実はこれが空き家問題が複雑化している要因の1つとなっています。例えば、Ⅹさんが亡くなって、Ⅹさんの相続人が長男Aと次男Bだったとします。相続財産である実家(空き家)は、ABの共有となり、AB両名の意見が一致しない限り、空き家の処分ができなくなります。そこで、両親が遺言書を作成する気持ちになったのであれば、不動産については「単独承継の内容」を勧めてみることも1つの方法です。「遺言者が所有する後記物件目録記載の不動産につき長男Aに相続させる。」といった旨の遺言が違法に作成されていると、空き家については、遺言者からダイレクトにAに単独承継されます。その代わり、次男Bには預貯金等の他の財産を相続させるといった調整がされるでしょう。
その結果、相続登記もAだけで申請できますし、空き家を処分しようと思えば、Aの一存で売却をしたり、解体をして更地にすることができます。単独承継をさせる旨の遺言があれば、少なくとも兄弟姉妹間で話がまとまらず、空き家の処分が進まない…という事態は防ぐことができます。併せて、実家の中に存在する動産についてもAに単独承継させる旨があるとよりスムーズに空き家の処分が進みます。ちなみに、法律上において「不動産」とは「土地と建物」のこと、「動産」とは「不動産以外」と定義されています。つまり、「動産」とは、土地と建物以外のお金であったり、自転車であったり、テレビであったり…と、すべての物を意味することとなります。

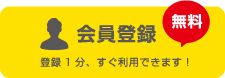
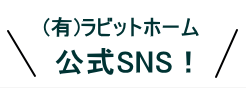
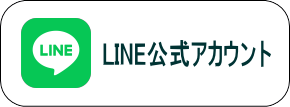









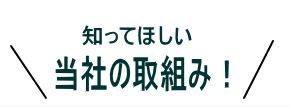


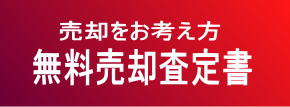
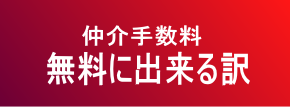
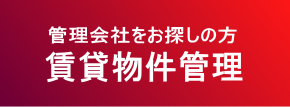

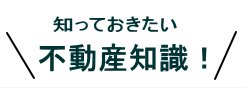
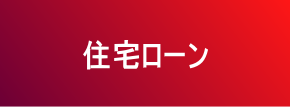





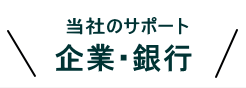




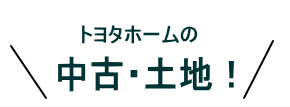
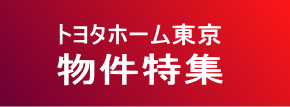
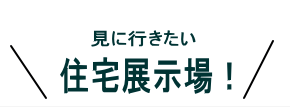
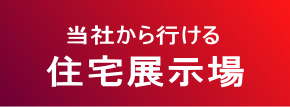
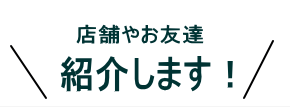


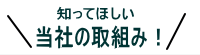


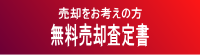

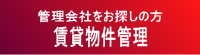

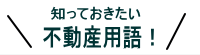
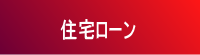





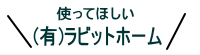


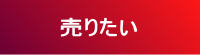

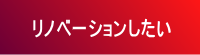

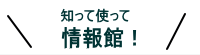

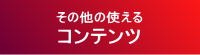
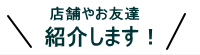

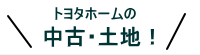
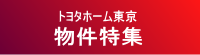
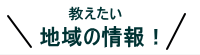



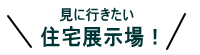
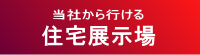
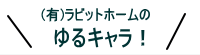

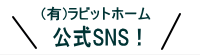






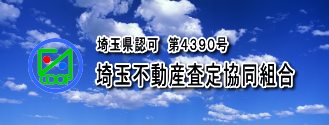

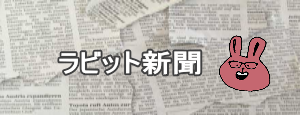




 ・売買会員ログイン
・売買会員ログイン